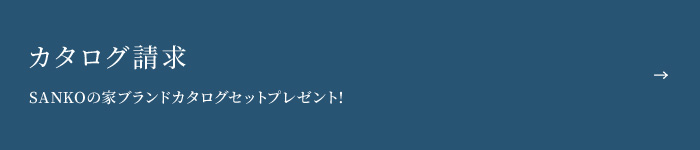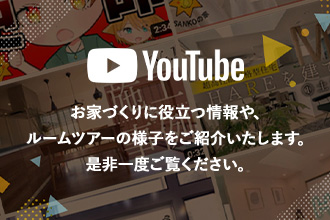カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
-
▼2026年(34)
-
▼2025年(362)
-
▼2024年(242)
-
▼2023年(143)
閉じる
2025.08.14
基礎換気口、なぜ見なくなったの?【設計お役立ち情報 Vol.52】

昔の家の基礎って、四角い穴が空いていたのを覚えていますか?
ネズミや猫が入らないように格子のカバーがついているもの。
これは「基礎換気口」といって、床下の湿気を逃がすためのものでした。
数十年前までは木造住宅では当たり前の仕様だったのですが、今の新築ではほとんど見かけません。
実は、これにはちゃんとした理由があります。
理由1:地震に弱くなる
基礎は家の重さを支える大切な部分。
そこに大きな穴を開けてしまうと、当然ながらその部分の強度が下がります。
地震に強い家づくりを目指す今では、穴を開けずに強度を保つ方法が選ばれるようになりました。
理由2:風の通りムラができる
基礎換気口は、場所によって風がよく通るところと全然通らないところができてしまいます。
空気が動かない場所の床下は湿気がこもり、カビや木材の腐食の原因に。
「換気しているつもりで、実は湿気を閉じ込めてしまう」という場合もありました。
理由3:施工が大変
間取りや基礎の形が複雑になると、穴の位置決めや施工が大変になります。
職人さんの負担が増え、精度に影響が出ることもあります。
こうした欠点を解決したのが「基礎パッキン構法」です。
基礎と土台の間にゴム製の通気パッキンを挟み、家の周囲すべてから均一に空気を取り込みます。
・基礎に穴を開けないから、強度が落ちない
・周囲全面から空気が出入りし、床下全体をムラなく換気できる
・湿気が土台に伝わりにくく、構造材の腐食を防げる
これにより、耐震性を高めながら床下の換気を確保できるようになりました。
床下の湿気はカビやシロアリ被害に直結するため、この進化はとても大きいです。
ちなみに、これらは床断熱を採用している場合の床下換気の方法です。
床断熱か基礎断熱かによって、使うパッキンの種類も変わるため注意が必要です。
床断熱(通気パッキン)
断熱材を1階床に入れる工法。
床下は外と同じ環境なので、外気を取り込む通気型パッキンを使います。
基礎断熱(気密パッキン)
断熱材を基礎の内側や外側に入れる工法。
床下は室内と同じ空間になるため、外気を入れない気密型パッキンを使います。
(SANKOの家では、こちらの基礎パッキンを採用。換気システムで換気を行っています。)
家づくりは日々進化しています。
基礎の中にも最新の知恵が詰まっているんですね。
松村