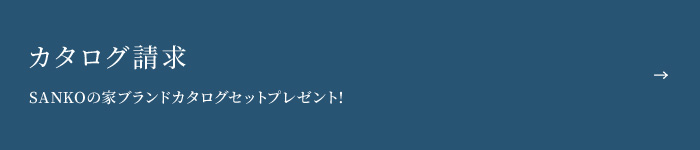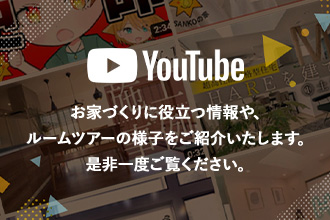カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
-
▼2026年(34)
-
▼2025年(362)
-
▼2024年(242)
-
▼2023年(143)
閉じる
2025.07.30
津波に備える家づくり|家族を守るために知っておくべき5つの視点【岡山注文住宅コラムVol.125】
岡山県の県南エリア【岡山市北区、中区、南区、東区、倉敷市、瀬戸内市、赤磐市、早島町、総社市、玉野市】で高性能住宅と自然素材にこだわり、健康で快適な注文住宅をご提案している工務店、SANKOの家です。

近年、各地で大きな津波被害が報道され、「自分たちの住まいは本当に安全だろうか」と不安を抱く方が増えています。特に小さなお子様がいるご家庭では、災害時のリスクを考慮した家づくりが重要なテーマとなっています。
この記事では、「津波に備える家づくり」をテーマに、家族の命と暮らしを守るために押さえておきたい5つの視点をQ&A形式で解説します。津波による被害の実例、浸水対策、地盤・土地選び、建物構造、防災教育まで網羅し、安心できる住まいのヒントをお届けします。
災害に強い家を建てたいとお考えの方、特に津波のリスクが気になる沿岸部にお住まいのご家族は、ぜひ最後までご覧ください!
目次
Q:津波災害で家はどのように倒壊するのか?
A:津波の水圧と漂流物の衝突によって家は倒壊します
津波が住宅に及ぼす影響は非常に大きく、1階部分が完全に水没するケースでは構造体そのものが大きく損傷します。特に木造住宅では、床下への浸水が進むことで基礎が浮き上がり、家全体が流される可能性があります。
東日本大震災では、築年数に関係なく多くの家が津波により倒壊し、特に海岸線から1km以内にある住宅は甚大な被害を受けました。
私たちも住宅見学のために訪れた被災地域で、1階が全壊しながらも、2階が奇跡的に残っていた木造住宅を目にした経験があります。その光景は「家の設計次第で命を守れる」と深く感じた出来事でした。
津波の被害は予想以上に甚大であることを念頭に置き、構造の工夫や高所への避難など、多重の備えが必要です。
Q:津波に備える家の浸水対策は何が有効ですか?
A:基礎のかさ上げと屋上避難を両立させた設計が有効です
浸水対策としてもっとも効果的なのは、1階の床をできるだけ高く設計することです。たとえば、標準的な住宅よりも基礎を30cm〜60cm高くするだけで、浸水被害のリスクは大幅に低減します。
また、床下部分に換気口を設ける際には、止水プレートや自動閉鎖式の防水設備を取り入れることで、津波や高潮の逆流を防ぐことができます。
加えて重要なのが、家からの「垂直避難」の手段を確保することです。屋上バルコニーや外階段、陸屋根(フラットルーフ)などを設けて、いざというときに2階以上に素早く避難できる設計が必要です。
Q:津波に強い土地の選び方は?
A:標高が高く地盤が安定した土地を選ぶのが基本です
津波のリスクを下げるには、「立地」が何よりも重要です。まずは国や自治体が公開している「津波ハザードマップ」や「浸水想定区域図」を確認し、津波の到達が想定されていない地域を候補に選びましょう。
さらに、地盤の強さも大切なポイントです。軟弱地盤は液状化や地盤沈下のリスクがあり、地震・津波の両方に弱くなります。地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を行うことで、家の安全性は大きく向上します。
同じエリア内でも標高2.5mと5mの土地で災害想定に大きな差があります。土地の価格や利便性だけでなく、「家族を守れる場所かどうか」を重視する視点が重要です。
Q:津波対策に適した構造や工法は?
A:高耐久木造と高気密・高断熱の組み合わせが災害への備えになります
津波対策においては、「構造の強さ」と「災害後も安心して住み続けられる室内環境」の両方を確保することが大切です。
SANKOの家では、長期優良住宅仕様の「高耐久木造」をベースに、通気工法による壁内の湿気対策や床下・屋根裏の換気設計など、劣化を防ぐ構造設計を標準としています。これにより、構造体の腐朽やカビの発生を防ぎ、災害後の復旧性も高まります。
さらに、気密性の高さも大きなポイントです。気密性が高いことで、外気や湿気、粉じんなどの侵入を抑え、室内の空気を清潔に保つことができます。特に津波や豪雨災害の後は、外部環境が一時的に悪化することが多いため、室内を衛生的かつ安全に保てる気密性は、暮らしを守る性能のひとつといえます。
ただし、気密性が高い=密閉空間になるため、機械換気が適切に機能していることが前提となります。
SANKOでは、気密測定(C値)をすべての住宅で実施し、換気設計にもこだわることで、健康かつ快適な住環境を実現しています。
津波に備える家づくりは、ただ構造を頑丈にするだけではなく、住んだあとの安心感と快適性まで考慮することが重要です。
Q:家づくりと防災教育はどう関係しますか?
A:設計と暮らしの両面から「命を守る力」を育むことができます
いざ津波が来たとき、最も重要なのは「早く避難できるかどうか」です。設計段階で避難動線を確保していても、家族で避難ルールを共有していなければ意味がありません。
家づくりと並行して、防災教育も始めましょう。月に一度、家族で避難経路の確認をしたり、津波警報アプリをスマートフォンに入れて使い方を確認したりするだけでも、非常時の対応力が格段に高まります。
SANKOの家では、設計士と一緒に「非常時の動線シミュレーション」を行いながらプランを練り、災害時にも冷静に行動できるような導線設計をご提案しています。
まとめ
「津波に備える家づくり」を実現するには、以下の5つの視点が不可欠です
-
津波被害のメカニズムを理解し、家の構造で対策する
-
浸水被害を想定し、かさ上げや屋上避難の手段を設ける
-
津波リスクの低い立地と強い地盤を選ぶ
-
高耐久木造+自然素材(無垢材・漆喰・珪藻土)で快適性と安全性を両立する
-
家族全員が避難行動を共有できるように防災意識を育てる
SANKOの家では、これらすべてを一貫してサポートし、「安心して暮らせる住まいづくり」をご提案しています。
岡山で新築住宅をご検討していらっしゃる方はモデルハウスにお越しください。
HEAT20 G3ランクの涼しく快適で、居心地の良い空間です。
高性能住宅を是非ご体感に来てみてください。