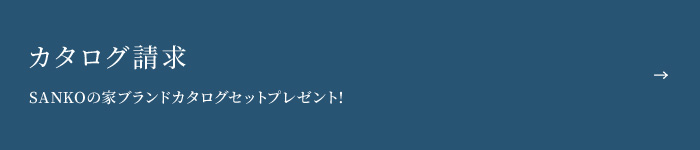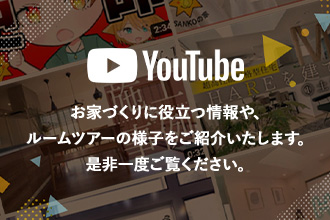カテゴリで絞り込む
ARCHIVE
過去の記事
-
▼2026年(34)
-
▼2025年(362)
-
▼2024年(242)
-
▼2023年(143)
閉じる
2025.10.16
色彩の面積効果について【設計お役立ち情報 Vol.53】

今年の二級建築士学科試験では、こんな問題が出題されました。
「住宅において、床、壁、天井の内装材の色彩は、一般に、天井面の明度を高く、床面の明度を低くし、全体的に彩度は低くする」
(答え:〇)
これは、室内を心地よく感じさせるための色彩計画の基本です。
彩度(あざやかさ)を抑えることで落ち着いた印象になり、さらに床 → 壁 → 天井の順に明度(明るさ)を上げることで、圧迫感のない空間が生まれます。
実は、色の印象は“どのくらいの面積で見るか”によって大きく変わります。
たとえば、小さなサンプルで見ると落ち着いたベージュでも、
外壁のように家全体に使うと、思ったより白っぽく見えることがあります。
これは、色彩の面積効果といい、人の目が広い面を見ると、
明るい色はより明るく、鮮やかな色に感じるためです。
つまり、面積が大きくなるほど色の特徴が強調されて見えるのです。
色選びの見本では上品なアイボリーに見えても、
家全体に塗ると真っ白に近い印象になります。
そのため、外壁など“広い面”に使う色は、「小さな見本よりワントーン暗め」を選ぶのがおすすめです。
室内でも起こる「面積効果」
この“面積効果”は、外観だけでなく室内でも同じです。
天井や壁を白くすると空間が広く見えて明るい印象になります。
床や建具を濃い色にすると落ち着いた雰囲気になる一方で、面積が広いと想像より暗く感じることもあります。
また、一般的には「天井を明るくする」ことで開放感が生まれますが
あえて天井を板貼りなど濃い素材にして落ち着いた空間に仕上げる、というデザインもあります。
リビングの一部や寝室など、「くつろぎ」を重視したい場所では、
このように“あえて暗くする”選択も効果的です。
「全体でどう見えるか」を考えながら色のバランスを整えていきます。
色選びは家づくりの楽しみのひとつ。
面積効果や明度のバランスを上手に活かして、
理想の“心地よい空間”をつくりましょう。
松村